 |
 |
|||||||||||||||||||
2019


「gift 2019 - イチゴイチエ de アリガトウ -」
不忍画廊のクリスマス企画のグループ展。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2019年12月6日(金)〜25日(水)
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:呉亜沙 / 亀井三千代 / サイトウノリコ / 櫻井結祈子 / 佐竹 広弥 / 繁田 直美 / 集治 千晶 / 鈴木明日香 / 鈴木 敦子 / 釣谷 幸輝 / 内藤 瑶子 / 中佐藤 滋 / 成田朱希 / 二階 武宏 / 花岡 幸 / 藤田 典子 / 藤田 夢香 / 馬籠 伸郎 / 三井田盛一郎 / 見崎 彰広 / 南舘麻美子 / 村上 仁美 / 安元 亮祐 / 山田 純嗣 / 山中現 / 山根 一葉

「ヴィーナスを綴じる in Edinbrgh」
「春画」や「エロス」をテーマに据え、絵画、立体、インスタレーションなどを発表。印刷されたイメージとしての版画や本を継ぎ目として、愛と美、笑いとユーモア、幸福感を持って”汲み尽くせぬ”新しいイメージを探求する展覧会。2018年10月3日~14日までアートコンプレックスセンター(信濃町)にて開催された展覧会を元に、作品とメンバーを拡充し、イギリスエジンバラで行なう展覧会。- 会場:ホワイトスペースギャラリー(76 East Crosscauseway EH8 9HQ Edinburgh)、
Scottish Art Club(24 Rutland Square EH1 2BW Edinburgh) - 会期:2019年11月6日(水)〜12日(火)(ホワイトスペースギャラリー)
2019年12月4日(水)〜2020年1月4日(土)(Scottish Art Club) - 主催:ヘイズ市川優衣
- 後援:Edinburgh University , Edinburgh College of Art
- 企画者:ヘイズ市川優衣
- 出品者:ABE daisuke|ICHIKAWA yui|ISHIMATSU chiaki |KAWASHIMA hiroyuki|KIMURA haruna |MIIDA seiichiro |MIYADERA raita|MORITA aya|O JUN|ROBINSON aiko|SUGAWARA moe|SUZUKI asuka|TAGA shin|TAKEUCHI erina|YAMADA junji|YOSHIDA jun
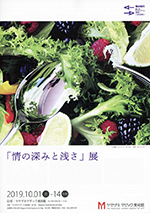
「情の深みと浅さ」
「情の時代」をテーマとするあいちトリエンナーレ2019に合わせて開催。あいちトリエンナーレは「情」の意味を「情報」の情、そして「情け」の情、と分析して、「情」から見える現代の姿を先端的な美術作品を通して見せようとしている。それに対して、「情」の奥行きと服装性をテーマに、愛知県内で活動するギャラリーがヤマザキマザック美術館の展示室の一部を使用して現代のアーティストを紹介する。- 会場:ヤマザキマザック美術館(名古屋)
- 会期:2019年10月1日(火)〜14日(月・祝)
- 主催:ヤマザキマザック美術館、NCAM (Nagoya Contemporary Art Map)
- 企画者:拝戸雅彦(愛知県美術館)
- 出品者:セシル・アンドリュ、深川瑞恵、藤原史江、ふるかはひでたか、原游、長谷川哲、蓮沼昌宏、加藤真美、河合里奈、公花、清河北斗、大森準平、松浦進、柴田麻衣、設楽陸、島本了多、髙木基栄、杉山健司、高橋大地、田中里奈、上田薫、山田七菜子、山田純嗣、山内喬博、吉田友幸
- 展覧会評、関連記事
「情の深みと浅さ」展覧会図録

「想像力 死んだ 想像せよ Imagination dead imagine」
不条理劇『ゴドーを待ちながら』で知られる作家サミュエル・ベケット(1906-1989)。演劇界だけでなくジャコメッティやデュシャンと交流があり、ボルタンスキーやダミアン・ハーストを始め多くの現代美術家達にも影響を与えている。2019年はベケット没後30年・ノーベル賞受賞50年の節目となる。今展はベケットが残した言葉《Imagination dead Imagine(想像力 死んだ 想像せよ)》からインスパイアされた4作家の新作を紹介する企画展。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2019年8月16日(金)〜31日(土)
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:會田千夏、設楽知昭、三井田盛一郎、山田純嗣

「アイチアートクロニクル1919-2019」
愛知県美術館は、2019年4月にいよいよ全館リニューアル・オープンを迎えます。そのちょうど100年前の1919年、東京の洋画グループ「草土社」に触発されて、愛知に暮らす10代20代の若者たちが一つの展覧会を開催しました。「愛美社」と名付けられたこのグループは、中央から強い影響を受けながらも、ここ愛知に軸足を置いて活動を展開します。本展は、この1919年を起点として、20-30年代の洋画壇やアヴァンギャルドの活発な活動、40-50年代の混乱と復興、60-70年代の反芸術やオフ・ミュージアムの傾向、80-90年代の現代美術を扱うギャラリーの増加、そして2000-10年代の官主導の公募展や芸術祭の隆盛にいたるまでの100年のあいだに、愛知の前衛的なアートシーンを様々なかたちで揺り動かしてきたムーブメントや事件を辿る企画です。愛知のアートの渦巻くような熱量を、愛知県美術館、名古屋市美術館、豊田市美術館をはじめとする地域のコレクションを通じてご紹介します。- 会場:愛知県美術館(名古屋)
- 会期:2019年4月2日(火)〜6月23日(日)
- 主催:愛知県美術館
- 特別協力:名古屋市美術館
- 企画者:愛知県美術館
- 出品者:青田真也、秋吉風人、浅井忠、あさいますお、浅野弥衛、味岡伸太郎、有馬かおる、安藤邦衛、安藤正子、安藤幹衛、猪飼重明、イケムラレイコ、市野長之介、伊藤髙義、伊藤利彦、伊藤敏博、伊藤廉、稲葉桂、今村文、岩田信市、魚津良吉、臼井薫、大﨑のぶゆき、大沢海蔵、大沢鉦一郎、太田三郎、大塚泰子、岡田徹、荻須高徳、小栗沙弥子、尾沢辰夫、加藤靑山、加藤静児、加藤延三、加藤マンヤ、川口弘太郎、河本五郎、岸田劉生、岸本清子、北川民次、北脇昇、鬼頭甕二郎、鬼頭健吾、鬼頭鍋三郎、木村充伯、河野通勢、久野真、久野利博、熊谷守一、倉地比沙支、栗本百合子、栗木義夫、黒田清輝、鯉江良二、河野次郎、小杉滋樹、後藤敬一郎、小林耕平、小林孝亘、斉と公平太、坂井範一、坂本夏子、佐藤克久、佐分眞、沢居曜子、設楽知昭、島田卓二、下郷羊雄、庄司達、白木正一、杉戸洋、杉本健吉、鈴木不知、清野祥一、関智生、ゼロ次元、染谷亜里可、竹田大助、田島二男、田島秀彦、辰野登恵子、東郷青児、東松照明、徳冨満、戸谷成雄、登山博文、中條直人、中野安次郎、奈良美智、西村千太郎、額田宣彦、野崎華年、野水信、長谷川繁、原裕治、櫃田伸也、平川祐樹、古池大介、ぷろだくしょん我S、堀尾実、眞島建三、松下春雄、三岸好太郎、三岸節子、水谷勇夫、宮脇晴、村瀬恭子、村松乙彦、森北伸、森眞吾、八島正明、矢橋六郎、山口勝弘、山下拓也、山田彊一、山田純嗣、山田睦三郎、山本悍右、山本高之、山本富章、横井礼以、吉川家永、吉川三伸、吉本作次、渡辺英司ほか
- 展覧会評、関連記事
「アイチアートクロニクル1919-2019」展覧会図録

「線の芸術Ⅱ 千差万別」
不忍画廊で2回目となる線の芸術展。「千差万別」と言うサブタイトルにあわせて、新作・コレクションとも様々な作品で構成される。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2019年2月4日(月)〜23日(土)
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:會田千夏、浅野勝美、池田俊彦、亀井三千代、柄澤齊、熊谷守一、古茂田守介、呉亜沙、駒井哲郎、サイトウノリコ、繁田直美、設楽知昭、 集治千晶、庄司朝美、鈴木明日香、田沼利規、中村正義、成田朱希、二階武宏、野見山暁治、長谷川利行、山田純嗣、山根一葉、ホルスト・ヤンセンほか

「Collection|近代美術 ⇄ Selection|現代美術」
近代美術と現代美術をいかにつなげるか…をテーマとした企画。近代美術コレクション+現代作家の新近作を「ヒトガタ」「イキモノ」「アルカタチ」「風景と静物」の4セクションで対峙させる。
- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2019年1月10日(木)〜26日(土)
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:相原求一朗、池田俊彦、池田満寿夫、一原有徳、岡本信治郎、門坂流、北川健次、呉亜沙、駒井哲郎、古茂田守介、サイトウノリコ、斎藤真一、作田富幸、設楽知昭、集治千晶、菅井汲、鈴木敦子、関根美夫、田沼利規、中村正義、成田朱希、二階武宏、橋場信夫、長谷川利行、浜口陽三、藤浪理恵子、見崎彰広、南桂子、元永定正、山口啓介、山田純嗣、山本鼎、山中現
2018

「gift 2018 ーイチゴイチエー」
アイン・ソフ・ディスパッチでの個展。名画をモチーフにしたシリーズの作品で構成。マグリット《白紙委任状》、酒井抱一《夏秋草図屏風》、伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》、ゴーギャン《我々はどこからきたのか?我々は何者か?我々はどこに行くのか?》、葛飾北斎《諸国瀧廻り》、土田麦僊《舞妓林泉》、マティス《赤いアトリエ》等、陰影表現をしていない絵画をモチーフに、近代絵画について考察する新作のインタリオ・オン・フォト作品と立体、ドローイング約10点を展示。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2018年12月3日(月)〜22日(土)
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:小林万里子/サイトウノリコ/集治 千晶/庄司 朝美/鈴木 敦子/田沼 利規/成田 朱希/花岡 幸/原 こなみ/藤田 夢香/藤浪理恵子/見崎 彰広/南舘麻美子/安元 亮祐/柳原 パト/山田 純嗣/山中 現
コレクションより|靉嘔/池田満寿夫/斎藤 真一/古沢 岩美/吉仲 太造/吉原 英雄 …他、 絵画・立体・貴重な美術資料など

山田純嗣展「絵画をめぐって - 影のない ll -」
アイン・ソフ・ディスパッチでの個展。名画をモチーフにしたシリーズの作品で構成。マグリット《白紙委任状》、酒井抱一《夏秋草図屏風》、伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》、ゴーギャン《我々はどこからきたのか?我々は何者か?我々はどこに行くのか?》、葛飾北斎《諸国瀧廻り》、土田麦僊《舞妓林泉》、マティス《赤いアトリエ》等、陰影表現をしていない絵画をモチーフに、近代絵画について考察する新作のインタリオ・オン・フォト作品と立体、ドローイング約10点を展示。- 会場:AIN SOPH DISPATCH(名古屋)
- 会期:2018年12月1日(土)〜15日(土)
- 主催:AIN SOPH DISPATCH
- 企画者:天野智恵子(AIN SOPH DISPATCH)
- 出品者:山田純嗣

「めがねと旅する美術展」
―視覚文化の探究―
現代は膨大な視覚情報が溢れている時代です。それらを「見る」ための器具として欠かせないのが、「めがね」です。視力を補うための装置であると同時に、「レンズ」もまた広義の「めがね」として、ミクロやマクロの世界を可視化したり、写真や映像となって、私たちに新しい世界観を提示してくれます。また、「色めがね」「おめがねにかなう」などの言葉があるように、「めがね」 にはものを見る際のフィルターといった意味が付されることもあります。
本展では、江戸時代後期の日本に視覚の革命を起こした、西洋由来の遠近法やレンズを用いた「からくり」にはじまり、列車や飛行機といった近代交通機関がもたらした新しい視覚、戦後から現代に至る目覚ましいサイエンス、テクノロジーの発展とともに変貌してきた視覚表現の軌跡を追います。あわせて、人類の普遍的な欲望である「秘められたものを見る」、 「見えないもの見る」ことの試みについても考察します。
本展は、「ロボットと美術」展(2010年度)、「美少女の美術史」展(2014年度)に続く「トリメガ研究所」企画の第3弾、最終章として「めがね」をキーワードに、江戸時代から現代までの「みること」に対する人々の飽くなき探求の営みをたどる視覚文化史展です。
- 会場:静岡県立美術館
- 会期:2018年11月23日(金・祝)~2019年1月27日(日)
- 主催:めがねと旅する美術展実行委員会
静岡県立美術館 - 企画:トリメガ研究所
- 協賛:ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
- 協力:株式会社東京メガネ、株式会社アートボックス
- 出品作家:
新井泉男、新井仁之/新井しのぶ、飯田昭二、家住利男、池内啓人、石内都、市川平、伊藤隆介、稲垣足穂、今和泉隆行(地理人)、入江一郎、岩崎貴宏、上田信、歌川国貞(二代)、歌川国貞(三代)、歌川重清、歌川豊春、歌川広重、歌川芳盛(二代)、江戸川乱歩、生賴範義、大洲大作、大畑稔浩、岡田半江、金氏徹平、金巻芳俊、岸田めぐみ、北尾政美、桑原弘明、黒川翠山、小池富久、小絲源太郎、五島一浩、今純三、今和次郎、佐竹慎、司馬江漢、鈴木理策、諏訪敦、高橋由一、高松次郎、田中智之、谷口真人、谷崎潤一郎、千葉正也、塚原重義、椿椿山、東京モノノケ、中ザワヒデキ、中村宏、七原しえ、丹羽勝次、野村康生、原在正、菱川派、平川紀道、不染鉄、前田藤四郎、松江泰治、松村泰三、松山賢、伝円山応挙、Mr.、棟方志功、元田久治、森村泰昌、門眞妙、安田雷洲、やぼみ、山口晃、山口勝弘、山田純嗣、山本大貴、宵町めめ、吉開菜央、吉田初三郎、米田知子、リュミエール兄弟、和田高広
東京大学大学院廣瀬・谷川・鳴海研究室+Unity Japan(松本啓吾、鳴海拓志、簗瀬洋平、伴祐樹、谷川智洋、廣瀬通孝)、東北芸術工科大学総合美術コース松村泰三研究室、東京大学大学院情報理工学系研究科廣瀬・谷川・鳴海研究室、北海道教育大学メディア・タイムアートコース映像研究室、めぐりあいJAXA実行委員会(五島一浩、澤隆志)、理化学研究所脳科学総合研究センター
- 出品作品・資料・装置
浅草・凌雲閣関連資料、アンティーク眼鏡、源氏物語屏風、重訂解体新書図譜、パノラマ画、眼鏡絵、洛中洛外図屏風、カメラオブスクラ、自働パノラマ鏡、ステレオグラム、ソーマトロープ、泰山鏡(眼鏡絵器具)、TVアニメーション「名探偵ホームズ」、反射式覗き眼鏡、ピープショウ、驚き盤(ヘリオシネグラフ)等
※出品作品・資料については変更される場合があります。また一部作品は前期(7/20~8/12)と後期(8/13~9/2)で展示替えを行います。 - 展覧会評、関連記事
「めがねと旅する美術」見えないものを見るための、世界ののぞき窓(青幻舎)

「めがねと旅する美術展」
江戸時代から現代まで-「みる」ことの探求
現代は膨大な視覚情報が溢れている時代です。それらを「見る」ための器具として欠かせないのが、「めがね」です。視力を補うための装置であると同時に、「レンズ」もまた広義の「めがね」として、ミクロやマクロの世界を可視化したり、写真や映像となって、私たちに新しい世界観を提示してくれます。また、「色めがね」「おめがねにかなう」などの言葉があるように、「めがね」 にはものを見る際のフィルターといった意味が付されることもあります。
本展では、江戸時代後期の日本に視覚の革命を起こした、西洋由来の遠近法やレンズを用いた「からくり」にはじまり、列車や飛行機といった近代交通機関がもたらした新しい視覚、戦後から現代に至る目覚ましいサイエンス、テクノロジーの発展とともに変貌してきた視覚表現の軌跡を追います。あわせて、人類の普遍的な欲望である「秘められたものを見る」、 「見えないもの見る」ことの試みについても考察します。
本展は、「ロボットと美術」展(2010年度)、「美少女の美術史」展(2014年度)に続く「トリメガ研究所」企画の第3弾、最終章として「めがね」をキーワードに、江戸時代から現代までの「みること」に対する人々の飽くなき探求の営みをたどる視覚文化史展です。
- 会場:島根県立石見美術館
- 会期:2018年9月15日(土)~11月12日(月)
- 主催:めがねと旅する美術展実行委員会
島根県立石見美術館 - 企画:トリメガ研究所
- 協賛:ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
- 協力:株式会社東京メガネ、株式会社アートボックス
- 出品作家:
新井泉男、新井仁之/新井しのぶ、飯田昭二、家住利男、池内啓人、石内都、市川平、伊藤隆介、稲垣足穂、今和泉隆行(地理人)、入江一郎、岩崎貴宏、上田信、歌川国貞(二代)、歌川国貞(三代)、歌川重清、歌川豊春、歌川広重、歌川芳盛(二代)、江戸川乱歩、生賴範義、大洲大作、大畑稔浩、岡田半江、金氏徹平、金巻芳俊、岸田めぐみ、北尾政美、桑原弘明、黒川翠山、小池富久、小絲源太郎、五島一浩、今純三、今和次郎、佐竹慎、司馬江漢、鈴木理策、諏訪敦、高橋由一、高松次郎、田中智之、谷口真人、谷崎潤一郎、千葉正也、塚原重義、椿椿山、東京モノノケ、中ザワヒデキ、中村宏、七原しえ、丹羽勝次、野村康生、原在正、菱川派、平川紀道、不染鉄、前田藤四郎、松江泰治、松村泰三、松山賢、伝円山応挙、Mr.、棟方志功、元田久治、森村泰昌、門眞妙、安田雷洲、やぼみ、山口晃、山口勝弘、山田純嗣、山本大貴、宵町めめ、吉開菜央、吉田初三郎、米田知子、リュミエール兄弟、和田高広
東京大学大学院廣瀬・谷川・鳴海研究室+Unity Japan(松本啓吾、鳴海拓志、簗瀬洋平、伴祐樹、谷川智洋、廣瀬通孝)、東北芸術工科大学総合美術コース松村泰三研究室、東京大学大学院情報理工学系研究科廣瀬・谷川・鳴海研究室、北海道教育大学メディア・タイムアートコース映像研究室、めぐりあいJAXA実行委員会(五島一浩、澤隆志)、理化学研究所脳科学総合研究センター
- 出品作品・資料・装置
浅草・凌雲閣関連資料、アンティーク眼鏡、源氏物語屏風、重訂解体新書図譜、パノラマ画、眼鏡絵、洛中洛外図屏風、カメラオブスクラ、自働パノラマ鏡、ステレオグラム、ソーマトロープ、泰山鏡(眼鏡絵器具)、TVアニメーション「名探偵ホームズ」、反射式覗き眼鏡、ピープショウ、驚き盤(ヘリオシネグラフ)等
※出品作品・資料については変更される場合があります。また一部作品は前期(7/20~8/12)と後期(8/13~9/2)で展示替えを行います。 - 展覧会評、関連記事
「めがねと旅する美術」見えないものを見るための、世界ののぞき窓(青幻舎)

「めがねと旅する美術展」
世界をとらえる、秘密をのぞく、次元を越える、だまされてみる?
あるいはレンズと鏡、そして技術革新と新視覚
現代は膨大な視覚情報が溢れている時代です。それらを「見る」ための器具として欠かせないのが、「めがね」です。視力を補うための装置であると同時に、「レンズ」もまた広義の「めがね」として、ミクロやマクロの世界を可視化したり、写真や映像となって、私たちに新しい世界観を提示してくれます。また、「色めがね」「おめがねにかなう」などの言葉があるように、「めがね」 にはものを見る際のフィルターといった意味が付されることもあります。
本展では、江戸時代後期の日本に視覚の革命を起こした、西洋由来の遠近法やレンズを用いた「からくり」にはじまり、列車や飛行機といった近代交通機関がもたらした新しい視覚、戦後から現代に至る目覚ましいサイエンス、テクノロジーの発展とともに変貌してきた視覚表現の軌跡を追います。あわせて、人類の普遍的な欲望である「秘められたものを見る」、 「見えないもの見る」ことの試みについても考察します。
本展は、「ロボットと美術」展(2010年度)、「美少女の美術史」展(2014年度)に続く「トリメガ研究所」企画の第3弾、最終章として「めがね」をキーワードに、江戸時代から現代までの「みること」に対する人々の飽くなき探求の営みをたどる視覚文化史展です。
- 会場:青森県立美術館
- 会期:2018年7月20日(金)~9月2日(日) ※会期中無休
- 主催:めがねと旅する美術展実行委員会
青森県立美術館 - 企画:トリメガ研究所
- 協賛:ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
- 協力:株式会社東京メガネ、株式会社アートボックス
- 出品作家:
新井泉男、新井仁之/新井しのぶ、飯田昭二、家住利男、池内啓人、石内都、市川平、伊藤隆介、稲垣足穂、今和泉隆行(地理人)、入江一郎、岩崎貴宏、上田信、歌川国貞(二代)、歌川国貞(三代)、歌川重清、歌川豊春、歌川広重、歌川芳盛(二代)、江戸川乱歩、生賴範義、大洲大作、大畑稔浩、岡田半江、金氏徹平、金巻芳俊、岸田めぐみ、北尾政美、桑原弘明、黒川翠山、小池富久、小絲源太郎、五島一浩、今純三、今和次郎、佐竹慎、司馬江漢、鈴木理策、諏訪敦、高橋由一、高松次郎、田中智之、谷口真人、谷崎潤一郎、千葉正也、塚原重義、椿椿山、東京モノノケ、中ザワヒデキ、中村宏、七原しえ、丹羽勝次、野村康生、原在正、菱川派、平川紀道、不染鉄、前田藤四郎、松江泰治、松村泰三、松山賢、伝円山応挙、Mr.、棟方志功、元田久治、森村泰昌、門眞妙、安田雷洲、やぼみ、山口晃、山口勝弘、山田純嗣、山本大貴、宵町めめ、吉開菜央、吉田初三郎、米田知子、リュミエール兄弟、和田高広
東京大学大学院廣瀬・谷川・鳴海研究室+Unity Japan(松本啓吾、鳴海拓志、簗瀬洋平、伴祐樹、谷川智洋、廣瀬通孝)、東北芸術工科大学総合美術コース松村泰三研究室、東京大学大学院情報理工学系研究科廣瀬・谷川・鳴海研究室、北海道教育大学メディア・タイムアートコース映像研究室、めぐりあいJAXA実行委員会(五島一浩、澤隆志)、理化学研究所脳科学総合研究センター
- 出品作品・資料・装置
浅草・凌雲閣関連資料、アンティーク眼鏡、源氏物語屏風、重訂解体新書図譜、パノラマ画、眼鏡絵、洛中洛外図屏風、カメラオブスクラ、自働パノラマ鏡、ステレオグラム、ソーマトロープ、泰山鏡(眼鏡絵器具)、TVアニメーション「名探偵ホームズ」、反射式覗き眼鏡、ピープショウ、驚き盤(ヘリオシネグラフ)等
※出品作品・資料については変更される場合があります。また一部作品は前期(7/20~8/12)と後期(8/13~9/2)で展示替えを行います。 - 展覧会評、関連記事
「めがねと旅する美術」見えないものを見るための、世界ののぞき窓(青幻舎)
日曜美術館「アートシーン」(NHK Eテレ)
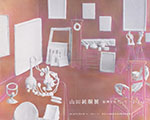
山田純嗣展「絵画をめぐって −2・3・2−」
2次元を3次元にし、それをまた2次元に戻すという制作のプロセスをテーマに、インタリオ・オン・フォトの作品に加えて、その制作過程で生じる立体とドローイングも併せて約20点をインスタレーション展示する。酒井抱一《夏秋草屏風》、葛飾北斎《諸国瀧廻り》、マティス《赤いアトリエ》等平面的な絵画をモチーフに、絵画について考察する作品で構成。- 会場:日本橋髙島屋 美術画廊X(東京)
- 会期:2018年6月6日−25日
- 主催:日本橋髙島屋
- 企画者:福田朋秋、荒木伸貴(髙島屋美術部)
- 出品者:山田純嗣
- 展覧会評、関連記事
山田純嗣「死・生・死」(山田純嗣展リーフレット)

「Through the veil 〜ベールを通して」
繁田直美|田沼利規|藤浪理恵子|山田純嗣
- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2018年6月6日〜23日
- 主催:不忍画廊
- 企画者:不忍画廊
- 出品者:繁田直美、田沼利規、藤浪理恵子、山田純嗣

「5COLORS」
主に平面作品の分野で活躍する5名の作家の展示を通して、絵画・ペインティングについて考察する企画。新作を中心とした展示。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2018年3月3日〜18日
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:會田千夏、大谷有花 、呉 亜沙、柳ヨシカズ 、山田純嗣

「グッとくる“絵”展・Ⅱ」
不忍画廊のコレクション、10年継続の現存作家、木村東介の愛した画家たちの3部構成の展覧会。- 会場:不忍画廊(東京)
- 会期:2018年1月12日〜27日
- 主催:不忍画廊
- 企画者:荒井裕史(不忍画廊)
- 出品者:池田満寿夫、一原有徳、駒井哲郎、浜口陽三、浜田知明、南桂子、池田俊彦、北川健次、
呉 亜沙、作田富幸、鈴木敦子、藤浪理恵子、安元亮祐、山田純嗣、山中現、大島哲以、
斎藤真一、中村正義、三上誠 他 - 展覧会評、関連記事
美術手帖2018年1月号『ART NAVI』
「すいらん創業41周年記念 もう一つの前橋の美術Vol.1」
2020年1月からアーツ前橋で開催される「前橋の美術2020」の関連展として、画廊翠巒でこれまで個展やグループ展を通して紹介し、活躍を続ける、または活躍を期待する作家のグループ展を「すいらん創業41周年記念展・もう一つの前橋の美術」として、2回に分けて開催致する。1回目は画廊翠巒で展覧会をする以外は、特に前橋には関係はないが、前橋という地、画廊翠巒でこれまで何度も発表し、前橋の美術に貢献してきた作家達のグループ展を開催する。